毎年正月に行われる箱根駅伝。2026年大会(第102回大会)の出場校は、いつ・どのように選ばれるのでしょうか?
この記事では、シード校制度や予選会の仕組み、具体的なスケジュールや注目ポイントまで、初めての方でもわかりやすく解説します。
特に「予選会はいつ開催されるの?」「シード校はどうやって決まるの?」といった疑問を持っている方に向けて、2026年大会の選考プロセスを時系列で整理しました。
この1本で、箱根駅伝をもっと深く楽しめるはずです。
箱根駅伝選考の全体像
箱根駅伝に出場できる20校は、前回大会の成績と予選会の結果によって決まります。
シード校制度とは!?
前回の箱根駅伝で総合順位10位以内に入った大学には、翌年の本大会への「シード権」が与えられます。これにより、予選会への出場は不要となり、本戦に自動的に進むことができます。成績上位校に安定した出場機会を保障する制度であり、毎年の競技力維持が求められます。
予選会の役割
シード権を持たない大学は「予選会」で本戦出場を争います。例年10月中旬に立川市で開催され、各校の上位選手の合計タイムで順位が決定。上位10校が翌年の箱根駅伝に出場できます。新興校や中堅校にとって、実力を示す大きなチャンスとなる大会です。
2026年箱根駅伝の選考スケジュール
箱根駅伝2026に向けて、予選会や出場校発表などの重要な日程はすでにおおよそ見通せます。
シード校発表の時期
シード校は、前年大会(2025年1月2・3日開催)で総合順位10位以内に入った大学に自動的に与えられます。
予選会開催日程
2026年大会の予選会は、2025年10月18日(土)に東京都立川市の陸上自衛隊立川駐屯地~昭和記念公園のコースで開催されます。出場資格を持つ大学が一斉に出場し、当日の合計タイムで上位10校が決定します。
シード校選考のポイント
シード校はどのように決まり、どのような条件で維持されるのか。制度の基本と注意点を整理します。
前年度大会成績によるシード付与条件
箱根駅伝における「シード校」は、前回大会の総合順位で10位以内に入った大学に自動的に与えられます。この順位は2日間(往路・復路)を通じた合計タイムで決まり、1区間の成績が極端に悪くても、チーム全体の底力でシードを確保するケースもあります。大会直後から次回大会のシードが確定するため、シーズン最終盤の目標として明確に位置づけられています。
シード校数と枠組み
シード枠は毎年固定で10校と決まっており、それ以外の大学はすべて予選会行きとなります。つまり、たった1つ順位を落とすだけで翌年は予選からの挑戦となるため、各校とも「10位以内死守」は至上命題です。
予選会での選考プロセス
シード校以外の大学が箱根駅伝に出場するには、この予選会を突破することが必須条件となります。
参加校の出場資格と申込方法
予選会には、関東学生陸上競技連盟に所属する大学であれば原則として参加が可能です。ただし、エントリーには出場資格があり、登録選手の一定人数が10000mやハーフマラソンで基準記録を満たしていなければなりません。申込は夏頃(例年8月末〜9月初旬)に行われ、エントリー選手の名簿と記録、チーム構成が提出されます。
予選会当日の流れと公式サイトでの速報確認
予選会は例年10月第3土曜日、東京都立川市の陸上自衛隊立川駐屯地〜昭和記念公園のコースで行われます。出場校は各校10〜12名が一斉にスタートし、上位10名の合計タイムで順位が決定されます。ゴール後すぐに速報タイムが発表され、正式な通過校リストは学生連盟の公式サイトや報道各社から当日中に発表されます。順位は団体戦のため、エース選手の活躍だけでなく、10番手の選手の走力が結果を左右するのも予選会の特徴です。
2025年大会の結果と2026年の出場校予想
前年大会の顔ぶれをもとに、2026年の出場校・注目校が見えてきます。
2025年大会シード校一覧(2026年大会のシード確定校)
以下の10校が総合順位10位以内に入り、2026年大会のシード権を獲得しました。
・青山学院大学(1位)
・駒澤大学(2位)
・國學院大学(3位)
・早稲田大学(4位)
・中央大学(5位)
・城西大学(6位)
・創価大学(7位)
・東京国際大学(8位)
・東洋大学(9位)
・帝京大学(10位)
2025年大会の予選会通過校(2024年予選会からの出場組)
2024年10月実施の予選会を勝ち抜き、2025年大会に出場した10校は以下です。
・立教大学(予選1位)
・専修大学
・山梨学院大学
・日本体育大学
・中央学院大学
・中央大学
・日本大学
・東京国際大学
・神奈川大学
・順天堂大学
予選会からシードを獲得した大学は?
上の通過校の中で、2025年大会本戦でさらに総合10位以内に入り、2026年のシード権を獲得したのは:
・中央大学(予選6位→本戦5位)
・東京国際大学(予選8位→本戦8位)
予選会からの“下剋上校”が翌年の出場権を掴んだ注目のケースとなります。
2026年選考の注目点と見どころ
予選会を勝ち抜く鍵を握るのはどの大学か?注目校や注目選手、シード争いの行方を予測します。
予選会通過ラインの目安
過去数年の結果から見ると、10番目の通過校は10人の合計タイムが概ね10時間40分台前後に集中しています。1人あたり63分台の走力が求められる計算になり、エースだけでなく中堅選手層の厚みが合否を分けます。2026年大会も例年同様のラインが想定され、「10番手の選手の走力」が勝負を決めるという予選会ならではの特性が変わることはないでしょう。
注目の“上がり目”校と再挑戦校
2025年大会で惜しくも出場を逃し明治大学や東海大学など、伝統校の巻き返しが期待されます。また、実力を伸ばしている東京農業大学や駿河台大学なども要注目です。例年、1〜2校は“予想外の大健闘”を見せる大学が出てくるのも予選会の魅力。直前のトラック記録会や合宿成果など、当日までの情報にも注目が集まります。
よくある質問(FAQ)
箱根駅伝の選考に関して、多くの人が疑問に感じるポイントをまとめました。
Q:選考結果はどこでいつ発表される?
予選会の結果は、レース終了後に関東学生陸上競技連盟の公式サイトで速報が公開されます。例年、当日のうちに出場校10校が発表され、ニュースサイトや駅伝専門メディアでもすぐに報道されます。シード校については、前回大会の順位によってすでに確定しているため、予選会のタイミングではすでに公知となっています。
Q:予選会に落ちたら、他の手段で出場できる?
基本的にはありません。予選会を通過できなかった大学には本大会への出場資格は与えられず、次年度の予選会から再挑戦することになります。ただし、予選会落選校から選手を選抜した「関東学生連合」チームが編成されるので、個人単体では出場の芽は残っています。
Q:シード校と予選会通過校の違いは何?
シード校は予選会を免除され、本大会への出場が保証された大学です。前年の実績により評価された形となり、秋の大会での疲労を最小限に抑えられるという利点があります。一方、予選会通過校は秋に最大のピークを持ってくる必要があるため、調整や故障管理が非常に難しく、大会当日に向けてコンディションを持続できるかが鍵になります。
まとめ
箱根駅伝2026の出場校は、前年大会の成績による「シード校」と、10月に開催される予選会を勝ち抜いた「予選通過校」によって構成されます。予選会は一発勝負の厳しい戦いですが、毎年ドラマが生まれ、駅伝ファンにとっても注目のイベントです。
特に近年は、実力が拮抗した中堅校が増え、わずかな差で明暗が分かれるケースも珍しくありません。シード争いや予選突破をめぐる駆け引き、選手たちの意地と覚悟がぶつかる舞台として、2026年の選考過程にも大きな期待が集まります。
出場20校がすべて出そろったとき、初めて「箱根駅伝」の物語が始まります。選考の過程も含めて見ていくことで、大会本番を何倍にも楽しむことができるでしょう。
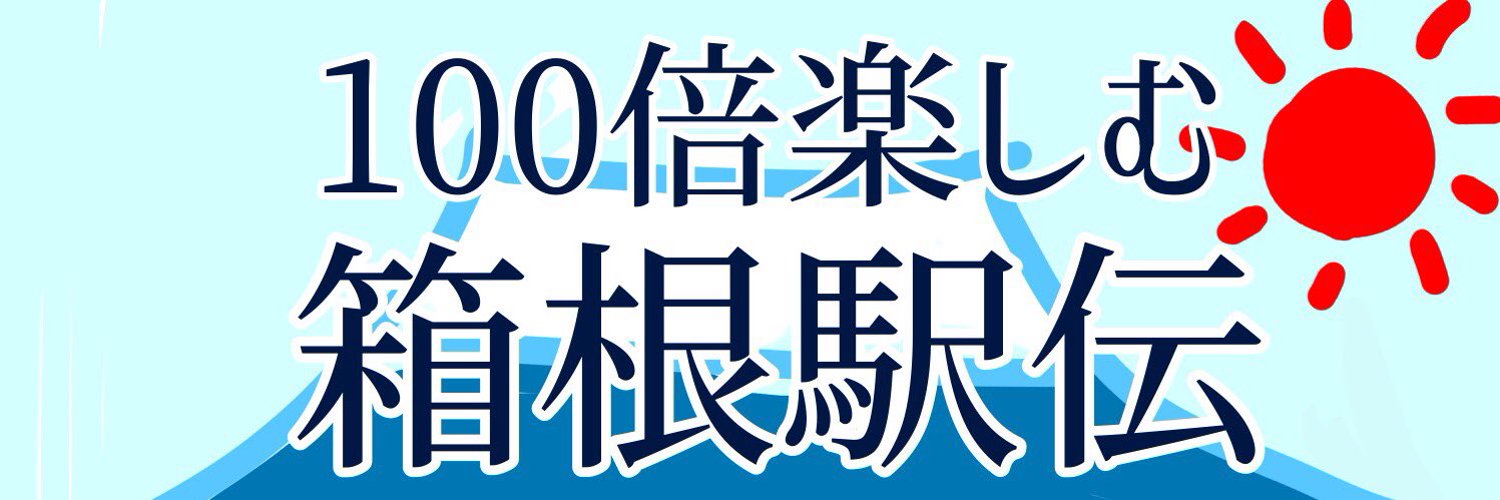
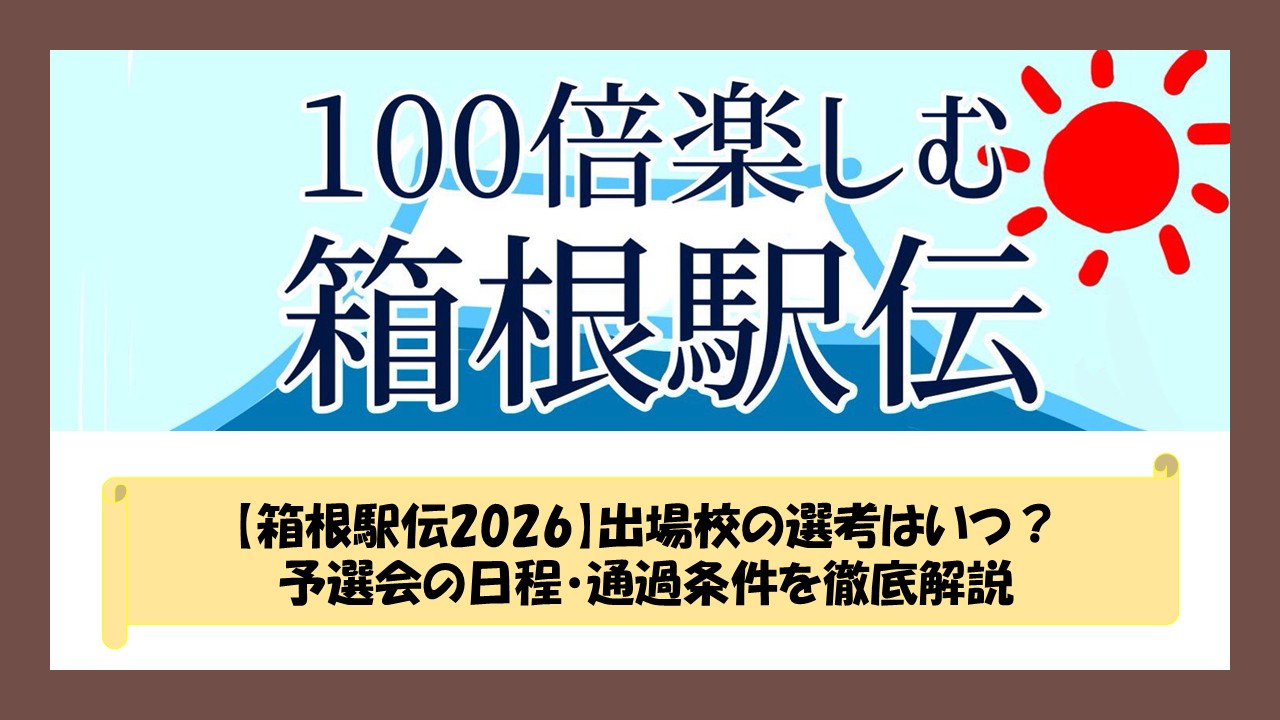

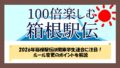
コメント